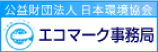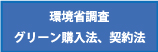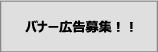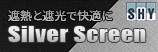- 【情報提供】CIRP LCE/Design 2026 サイドイベント GINP ワークショップ in Japan― 企業実務に活かす「絶対的サステナビリティ」 ―Absolute Environmental Sustainability(AES)を測り・設計し・実装する(3/13・神奈川,3/17・東京)
- 【情報提供】デジタルトリプレット実践研究会 公開シンポジウム「暗黙知のデータ価値化を切り拓くデジタルトリプレットーデジタルツインからデジタルトリプレットへ進化する日本型ものづくり」(4/14・東京)
- 【環境省】「環境表示ガイドライン」の改定案に対する意見募集(2/16~3/17)
- オンラインミニセミナー「サーキュラーエコノミーを加速する水平リサイクル・アップサイクルの取り組み」【埼玉GPN】(3/11)
- 事務局臨時閉局のお知らせ(2/16 11時~16時)
ISO14001やエコアクション21におけるグリーン購入の運用方法などを知りたい【企業向け】
企業や団体等が環境問題へ取り組む場合、PDCAサイクルに沿って組織的に取り組むことが有効とされています。PDCAサイクルに沿って組織的に取り組む方法や仕組みを環境マネジメントシステムと呼びます。
その代表的な仕組みに、ISO14001やエコアクション21があります。
その他、地域で独自に開発されたり、中小企業向けに開発されたりした仕組みに、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードやエコステージ等があります。
これらの環境マネジメントシステムは、第三者が取り組みを審査し、認証や登録を行う仕組みとなっています。
環境問題に取り組む際、事業所から排出される廃棄物の削減や電力使用量の削減から始める事例が多く見受けられますが、環境マネジメントシステムの認証を受けたり、登録したりする場合、廃棄物の削減や電力使用量の削減といった出口対策だけではなく、入口対策としてのグリーン購入に取り組むことも必要になります。エコアクション21(2017年版ガイドライン)では、グリーン購入は推奨事項として継続的に取り組むことが位置づけられています。
企業では、環境マネジメントシステムの中で環境方針を策定したり、経営方針の中に環境保全やCSRの取り組みを位置づけたりすることがあります。グリーン購入についても、それらの方針や企業としての取り組みにおける位置づけを検討し、目標や計画を立てることが大切です。
企業が購入したり発注したりするものは、大きく以下の四つに分けることができます。
①自らのオフィス内で使用する物品・サービスの購入・発注
②製品・サービスを提供するための部品・原材料・サービスの購入・発注
③顧客にグリーン購入を促す
④事業者を選ぶ(上記①及び②に付随)
グリーン購入に関する目標や計画を立てるためには、まず自社の物品・サービスの購入・発注状況を把握することが大切です。
インパクトの大きい分野は何か(自らの事業活動が負荷を与えていると考えられる分野や環境影響が大きく、組織での購入量が大きい分野等)という視点や、取り組みやすさ(環境配慮商品が入手しやすく、コストがあまり上がらない分野等)という観点から検討することが良いでしょう。
上記①について、取り組みやすさという観点では、「エコ商品ねっと」掲載商品やエコマーク等の環境ラベルを参考に対象品目と調達ルールを作ることが効率的です。
上記②について、環境ラベル等がない場合もあることから、取引先と情報を交換したり、他社の取り組み事例を収集したりすることも有効です。
企業としては、自社の本業と環境活動とのつながりを強くするために、自社の環境配慮型製品・サービスの製造・販売(上記③に該当)を目標に定めることも良いでしょう。
取り組んだ結果を把握し、社内で共有するとともに、外部へ公表することも大切な取り組みです。
環境マネジメントシステムに取り組む企業のうち、環境報告書やホームページ等で活動結果を公表している企業は多数あります。
目標を達成できたのかどうかという結果はもちろん、達成できた要因や達成できなかった要因を分析し、改善していくことが大切です。
上記①にとどまらず、社会動向に対応して上記②や③、社会面にも配慮した購入への拡大等、活動をステップアップさせていきましょう。
<参考>
環境に配慮した事業活動の促進(環境省ホームページ)
ISO14001(環境省ホームページ)
エコアクション21
KES・環境マネジメントシステム・スタンダード
エコステージ