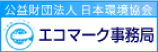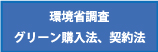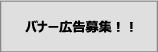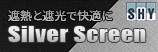- 【情報提供】CIRP LCE/Design 2026 サイドイベント GINP ワークショップ in Japan― 企業実務に活かす「絶対的サステナビリティ」 ―Absolute Environmental Sustainability(AES)を測り・設計し・実装する(3/13・神奈川,3/17・東京)
- 【情報提供】デジタルトリプレット実践研究会 公開シンポジウム「暗黙知のデータ価値化を切り拓くデジタルトリプレットーデジタルツインからデジタルトリプレットへ進化する日本型ものづくり」(4/14・東京)
- 【環境省】「環境表示ガイドライン」の改定案に対する意見募集(2/16~3/17)
- オンラインミニセミナー「サーキュラーエコノミーを加速する水平リサイクル・アップサイクルの取り組み」【埼玉GPN】(3/11)
- 事務局臨時閉局のお知らせ(2/16 11時~16時)
【提言】「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)改正案」に対する意見を提出しました
GPNは、経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課に対し、「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)改正案」に対する意見を提出しました。
改正FIT法の施行から1年を迎える中、状況の変化等を踏まえ、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会等の各委員会において、認定実務の改善を通じた再生可能エネルギー発電事業の適正化を含め、FIT制度の運用の在り方に関する議論が行われています。
各委員会における議論の成果・決定事項、必要な措置を2018年度以降のFIT制度の運営に反映させるべく、資源エネルギー庁では、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の関係省令及び告示の改正や、事業計画策定ガイドラインの改正に向けた検討が進められています。
詳細≫ 事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)改正案に関するパブリックコメントについて(2018年3月17日受付終了)
GPNの意見≫「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)改正案」に対する意見[PDF174KB]
【GPNの意見】
■第2章 第1節「3.5農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」に対して
・意見内容
RSPO認証制度などを活用することで、パーム油発電の燃料に対して環境・社会面の配慮を求めたことは大いに評価できる。さらに非認証油を混ざることなく管理された認証油を用いるとしたことも評価できる。
しかしながら発電に使用されるバイオマスはその生産・輸送過程において大きなCO2排出源となる例もあり、個々の燃料についてのライフサイクル評価が重要である。認証材であれば良しとするのではなく、木質系、農産物系、廃棄物系全てにおいて、「個々の燃料についてのLCC評価(ライフサイクルカーボンの算出と評価)を行い、その結果を事業者で把握し、環境負荷を低減していくことが望ましい」とする必要がある。
・理由
RSPOの認証制度とは別に、現在ISPOとMSPOという認証制度がそれぞれインドネシア政府、マレーシア政府により推進されており、現状では流通量が少ないが、2年後の2020年を目指して義務化することを目標としている(参考1)。義務化が実現されると両国で生産されるパーム油はすべて環境・社会面に配慮した第三者による認証油ということになる可能性があり、本ガイドラインで明確にした持続可能性の確認方法は有効性がなくなる恐れがある。パーム油に限らず、輸入されるバイオマスは特に、その輸送過程や土地利用転換によるCO2排出量が大きいことから、認証材であれば良しとするのではなく、燃料自体のLCC評価(ライフサイクルカーボンの算出と評価)と、その負荷低減を事業者へ求めていくことが重要だと考える。
また、国内の木材利用は、森林の荒廃抑制・地域資源の有効利用・エネルギー自給率の向上・地域の経済循環率の向上などにもつながる。バイオマス燃料のLCC評価を推進することは、国内の木材利用を促進することにもつながると考える。
英国の場合、バイオマス発電を行う場合には従来の化石燃料に比べて温室効果ガス排出を6割削減することという基準が既に設けられている(参考2)。
参考1≫ 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会:持続可能な調達ワーキンググループ 第17回資料
参考2≫ バイオマス産業社会ネットワーク(BIN):シンポジウム「固体バイオマスの持続可能性確保へ向けて~英国の事例と日本の課題~」資料