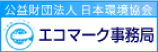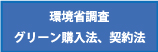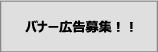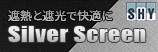- 【情報提供】CIRP LCE/Design 2026 サイドイベント GINP ワークショップ in Japan― 企業実務に活かす「絶対的サステナビリティ」 ―Absolute Environmental Sustainability(AES)を測り・設計し・実装する(3/13・神奈川,3/17・東京)
- 【情報提供】デジタルトリプレット実践研究会 公開シンポジウム「暗黙知のデータ価値化を切り拓くデジタルトリプレットーデジタルツインからデジタルトリプレットへ進化する日本型ものづくり」(4/14・東京)
- 【環境省】「環境表示ガイドライン」の改定案に対する意見募集(2/16~3/17)
- オンラインミニセミナー「サーキュラーエコノミーを加速する水平リサイクル・アップサイクルの取り組み」【埼玉GPN】(3/11)
- 事務局臨時閉局のお知らせ(2/16 11時~16時)
【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表①(2025年度)
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、「持続可能な調達(消費と生産)の推進を通じて、SDGsの目標達成やカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します」という活動方針のもと、セミナー等を通じて、サステナビリティの様々なテーマの情報発信に取り組んでいます。
今回、特別企画として、SDGsが採択された9月25日に合わせ、GPN会員団体・アドバイザーより、SDGsの目標達成に向けて、サステナビリティに取り組む重要性・必要性をテーマにメッセージを募集し、52団体(アドバイザーを含む)の方にご協力いただきましたので、ご紹介いたします。
メッセージは、2つの記事にわけております。

【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表①(2025年度)
<団体等五十音順>
・一般社団法人アニマルウェルフェア・コーポレート・パートナーズ (AWCP) 代表理事 上原まほ
・氏家 啓一GPN理事・アドバイザー(Global Compact Network Japan BHR Specialist)
・株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 代表取締役社長 中山東太
・特定非営利活動法人えこひろば 代表理事 阿部晴子
・株式会社エコリカ 代表取締役 宗廣 宗三
・株式会社SHY
・FYS株式会社 執行役員 APRES事業部長兼経営企画室長 井口 洋
・elsa
・株式会社オカムラ
・小川珈琲株式会社
・加山興業株式会社
・川崎キングスカイフロント東急REIホテル
・NPO法人環境自治体会議環境政策研究所 理事長 小澤はる奈
・株式会社クラウン・パッケージ
・コクヨ株式会社
・コマニー株式会社
・株式会社コングレ
・SAGA COLLECTIVE協同組合
・佐賀市 総務部副理事兼契約監理課長 山口和海
・有限会社サステイナブル・デザイン
・札幌市円山動物園 保全・教育担当係長 佐竹 輝洋
・サラヤ株式会社
・一般財団法人CSOネットワーク
・ジット株式会社
・株式会社スーパーホテル
・スーパーバッグ株式会社
【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表②(2025年度)
■一般社団法人アニマルウェルフェア・コーポレート・パートナーズ (AWCP) 代表理事 上原まほ
“アニマルウェルフェアの未対策は投資のリスクに”
サステナビリティは、もはや企業の「良いこと」ではなく、生き残りのための必須戦略です。資源の枯渇、気候変動、そして厳格化する規制は、企業の存続そのものを直接的に脅かしています。これらのリスクを回避し、逆境に負けないレジリエントな企業へと変革するためには、サステナビリティへの真剣な取り組みが欠かせません。この活動は、財務諸表に現れない非財務価値を高め、結果として企業の価値全体を向上させるのです。
特に、家畜の福祉を向上させるアニマルウェルフェアへの配慮は、企業の倫理観と社会的責任を問う重要な試金石です。グローバル企業3,000社以上が「100%ケージフリーの鶏卵を調達する」と公約するなど、これは世界基準となりつつあり、欧州やアメリカの複数州ケージ飼育そのものが法的に禁止され始めています。
動物を単なる生産手段と見なす旧来のビジネスモデルは、SNSによって劣悪な飼育環境が瞬時に拡散され、ブランドを致命的に傷つける危険をはらんでいます。しかし、問題はそれだけではありません。新型コロナウイルスのような新興感染症の60%は、動物由来の人獣共通感染症です。実際にアメリカでは乳牛で確認されたH5N1亜型インフルエンザは、牛間のみならず、人を含む哺乳類にも感染しているのです 。
アニマルウェルフェアを尊重することは、食の安全を守り、未来のパンデミックを防ぐための重要な投資なのです。この取り組みは、企業のブランド価値と社会的信用を高め、ESG投資を重視する投資家からの信頼と資金を引き寄せます。アニマルウェルフェアは倫理的選択であるだけでなく、リスク管理とリスク管理と競争優位性を築くための、不可欠な要素です。
■氏家 啓一GPN理事・アドバイザー(Global Compact Network Japan BHR Specialist)
SDGs採択から10年が経ちました。「持続可能」の定義は多様にあります。国連では「将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす」ことであり、企業においては「利益(Profit)、人(People)、地球(Planet)の3つを同時に追求する」と言う考え方が近いでしょう。市民社会的には、「公正、繁栄、環境保護の価値観」で捉えられ社会正義や幸福も含まれます。それぞれが思い思いの角度で臨むことができるのがSDGsの特徴です。さて世界全体の進捗については、国連経済社会局のSDGs報告2025によると、軌道に乗っているか緩やかに進捗しているターゲットは35%に留まると報告されています。
日本は、目標5(ジェンダー平等)、目標12(つくる責任つかう責任)、目標13(気候変動)などが深刻な課題ありと評価されました。一方、これまで、企業と市民社会や地方自治体が連携してSDGsに取組んでいるのも周知のことです。グリーン購入ネットワーク(GPN)では環境情報データベース「エコ商品ねっと」を通して、国際的な省エネ基準、カーボンオフセット、国際エネルギープログラム、リサイクル材料などの基準に基づき、消費者のエシカル購入を推進してきました。「十年の計は木を植える」の例えのように、これまでの仕掛け・取組みが、残りの5年に結実することを信じて、取組みを続けていきたいと思います。
■株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 代表取締役社長 中山東太
持続可能な社会づくりは、環境に配慮した製品の選択から始まります。
当社は、グループ会社のグリーンプラ株式会社とともに、PPバンドの水平リサイクルに取り組んでいます。他社に先駆けて使い捨てプラスチックをマテリアルリサクルすることで、製品の環境負荷低減とコスト低減により他社と差別化し、売上増加を目指しています。今後とも、再生材料を用いた製品の製造も積極的に行うことで、限りある資源の循環活用と、雇用増加により地域社会の持続可能性に貢献していきたいと思います。
消費者の皆様には、グリーン購入の観点で弊社製品を梱包材に選んでいただいている企業様の取り組みを評価いただき、応援していただきたいです。
■特定非営利活動法人えこひろば 代表理事 阿部晴子
この数年、猛暑や豪雨水害が増え、異常気象が“普通”になってきたことに強い危機感を感じています。「人類が資源やエネルギーを使い捨てる生活を続けていけば、あと30年後には気候危機が加速し、地球が持続可能ではなくなるので対策が必要」との話は、国際社会でも個人の暮らしのレベルでも何度となく聞いていてもう待ったなしの状況ですが、終わらない戦争や異常気象による災害のニュースにかき消されているようです。選挙でも、経済対策が最優先で、残念ながら気候危機対策は殆ど争点になりませんでした。
資源やエネルギーを大切にする暮らしを地域で広げたいと小さな活動を始めてから約25年経ちます。相変わらず便利さ優先で、使い捨て品の多さや無駄な電気やエネルギーの使い過ぎに社会全体が慣れてしまっていることを痛感しています。持続可能な社会、地球にするために、企業、個人、自治体など様々な立場でできることから取り組みたいですね。そして、国には気候危機を食い止める抜本的な対策の推進と国民への協力の呼びかけを期待しています。協力したい人たちは大勢いますので。
■株式会社エコリカ 代表取締役 宗廣 宗三
私たちエコリカは、「限りある資源を未来へつなぐ」という理念のもと、リサイクルインクカートリッジをはじめとする環境配慮型製品の企画・開発・販売を通じて、循環型社会の実現を目指してまいりました。
地球環境は今、気候変動・資源の枯渇・海洋プラスチック問題など、深刻な課題に直面しています。これらは決して一部の国や地域だけの問題ではなく、私たち一人ひとり、そして企業にとっても無関係ではありません。
サステナビリティへの取り組みは、環境保全だけでなく、企業の持続的成長や社会的信頼の獲得にも直結しています。とりわけ製品ライフサイクル全体を見直し、資源の「使い捨て」から「再利用・再生」への転換を図ることは、未来の世代への責任であると考えています。
エコリカは、今後もパートナー企業・自治体・お客様と連携しながら、「使い終わったら、終わりではない」という価値観を広め、持続可能な社会づくりに貢献していきたいと考えております。
■株式会社SHY
株式会社SHYは、遮光・省エネ効果を備えたロールスクリーンやフィルムなど、環境に配慮した製品の開発・提供を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいりました。
創業以来、「人と環境に優しい製品づくり」を使命とし、遮熱・遮光製品をはじめとする取り組みを通じて、エネルギー消費の抑制と快適な空間づくりを両立させています。
私たちは技術を結集し、価値のある環境をつくることを目指してきました。
こうした技術は、環境負荷の低減に直結し、地域社会から地球規模までつながる課題解決に寄与しています。
SDGsが掲げる目標は、世界共通の道しるべであると同時に、私たち一人ひとりの行動指針です。
地元・三重県津市から発信する製品と技術を通じて、地域とともに歩みながら、持続可能な未来の実現に力を尽くしてまいります。
■FYS株式会社 執行役員 APRES事業部長兼経営企画室長 井口 洋
弊社はアパレル副資材(ハンガー、透明袋など)を取り扱っている会社であります。7年程前より広域認定取得企業としての使命感から、昨今の重要課題である「プラスチックごみ削減」に向けて、自社で扱うプラスチックハンガーを現場(店頭)より回収して、再利用する循環システムを構築してまいりました。このスキームAPRES(アプレス)と名付けて、アパレル大手リテーラー様に対してAPRES循環システム採用に向けての啓蒙活動を行っております。
従来型とAPRESの違いは以下の通りです。
【従来型】店頭に届いた商品(洋服)からプラスチックハンガーを取り外し陳列用ハンガーに掛け替える。掛け替え後、不要になったプラハンガーを各商業施設所定のハンガー処理場に移動。商業施設に一定量たまったプラハンガーを廃プラ回収業者が回収。回収されたプラハンガーは、そのほとんどが焼却処理⇒CO2排出。
【APRES型】店頭でハンガーの掛け替えまでは従来どおりですが、不要になったハンガーは、現場にて箱にため置き、一定量になると弊社提携の運送業者に回収依頼をし、店頭まで回収。 回収された箱入りハンガーは弊社のセンターに運送され、選別・品種ごとに仕分けし、再出荷しております。⇒廃プラはゼロ⇒焼却によるCO2の排出もゼロ (環境面貢献)
また、廃プラ処分代を請求する商業施設様も有りますがAPRESスキームでは回収に関わるコストは一切発生いたしませんので、従来型比較より経済効果も有ります。(経済面貢献)
更に、取組先様には、出荷量・回収量・CO2排出削減量を数値化し「数字の可視化報告」を行っております。取組先様の中にはこの可視化した年間数字を株主総会・IR情報等で発表されている企業様もございます。(社会面貢献)
次に、処理後、商品ハンガーとして再利用できないものもございますが、再出荷できないプラ原料を再生チップ化して“食器・事務用品などのノベルティグッズ提案”「御社から回収したハンガーでリユースできない原料で●●を作ってみました、よろしければ、ノベルティグッズとして」いかがでしょうか?」のような提案も今後は行っていきたいと考えております。(企業イメージ貢献)
いずれにしましても。従来型の廃プラ焼却では無くAPRES循環型を普及させ業界全体で廃プラ削減に貢献して、環境保全の一助になればと願っております。また今後は商業施設様も巻き込んで、更なる廃プラ削減に努力したいと考えております。
■elsa
当団体は「昨日の自分よりも1%だけ、世界や自分のために変えてみる」を掲げ、小さな取組みでも、ちょっとだけでも、少しずつ持続可能な社会に向かっていく、そんな社会の実現を目指しています。
持続可能性(サステナビリティ)とは、「将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすために、環境、社会及び経済のバランスを実現すること」の意味で使われています。サステナビリティの取組みは、特定組織の関心だけでなく、環境・社会・経済の3つの側面を含むより広範な関心から総合的発展を目指す活動を指すため、ひとつの組織だけで注力せず、様々な関係者が相互に連携していくことが重要であると考えています。
私たちはこれからも、サステナビリティ課題の解決に向けてみなさまと連携した取組みにチャレンジしていきます。
■株式会社オカムラ
オカムラグループは、パーパスである「人が活きる社会の実現」に向け、「豊かな発想と確かな品質で、人が活きる環境づくりを通して、社会に貢献する。」をミッションとしています。
「人が活きる社会の実現」にはサステナビリティを中心に捉えた事業活動が重要であるとの考えのもと、事業活動の経済的側面と同時に社会的側面・環境的側面の重要性を認識し、「オカムラグループ サステナビリティ方針」を掲げ、企業の社会的責任を果たす経営に取り組んでいます。マテリアリティ(経営の重要課題)を特定するとともに、そのリスクの低減と機会の創出に向けて、「人が活きる環境の創造」「従業員の働きがいの追求」「地球環境への取り組み」「責任ある企業活動」の4つの分野で活動を推進しています。「責任ある企業活動」を経営基盤とし、「従業員の働きがいの追求」によって一人ひとりが働きがいを感じるとともに、「地球環境への取り組み」を実践することでサプライチェーン全体を通じて環境負荷を低減してまいります。また、事業活動を通じた「人が活きる環境の創造」により、人々が笑顔で活き活きと働き暮らせる社会の実現に貢献します。
■小川珈琲株式会社
弊社は「私達は珈琲職人として、未来をつなぐ本物の価値を創造し、真心を持ってお届けする。」という理念を掲げ、その体現に向けて日々活動をしております。この理念体現には品質の良いコーヒー豆を持続的に調達する必要があります。
品質の良いコーヒー豆の栽培には豊かな自然環境が必要で、安定調達のためにはその環境が持続しなければなりません。また、生産者の手間暇かけた丁寧な栽培も必要で、生産者の暮らしも安定したものでなければならないと考えております。
「自然環境」と「人」が必要不可欠ななかで、弊社が大切にしていることは実際に「会いにいく」ことです。生産者と交流することで、私たちが求めるコーヒーが生産される現場を直接見て、対話を繰り返し、信頼関係を築くことで品質の良い、安定したコーヒー豆の調達が可能になると考えています。
こうした活動の中で、国際フェアトレード認証、や有機栽培コーヒー、バードフレンドリー®認証、オランウータンコーヒー等、私たちの考えとも通じるサステナブルでエシカルな認証と出会い取り組み始め、現在では多くの消費者にお届けすることができております。
私たちが扱う、コーヒーは生産者と生活者のたくさんの方が関わっており、課題解決能力は大きいと考えます。コーヒーサプライチェーンの真ん中のロースターとして、こうした取り組みを続けることが、コーヒー文化を未来へとつなげていくものと信じています。
・一杯のコーヒーからできること
■加山興業株式会社
「Our Planet, Our Home」=私たちの惑星(地球)は私たちの家である。加山興業は「緑あふれる」=豊かな自然環境、「クリーンな」=廃棄物のない、自然エネルギーの利用、「日常」=ありふれた毎日こそが幸せであり、地球に暮らす全ての生き物が共存共栄し、幸せに暮らすことができる世界の実現を目指すことをありたい姿として捉えています。
それを実現する上で、環境や社会に与えるインパクトが大きく且つ自社が強みとしている廃棄物中間処理業、環境ソリューション事業等バリューチェーン全体を考慮して、「資源循環・適正処理」「脱炭素」「地球共生」「環境共生」「ウェルビーイングの追求」「コンプライアンス遵守・リスクマネジメント」という6つのサステナビリティ領域における重要課題を設定しています。
「資源循環・適正処理」については、あらゆる廃棄物の適正処理を継続して満たしていくこと、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクル等新たな事業領域の挑戦を通じたサーキュラーエコノミー経済への貢献を目指していきます。「脱炭素」については2050年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みを通じた、「クリーンな日常を世界に」 につながる社会創造への貢献を目指していきます。「地球共生」については、様々な社会課題に対してマルチステークホルダーとのエンゲージメントを重視しながら柔軟に応え続けることができる”I’m Here! ” (いつもそばに)の体現を目指していきます。「環境共生」については、「緑あふれる」=自然環境と生態系を豊かにする整備を目指していきます。「ウェルビーイングの追求」については、社員がお互い尊重し高め合い、安寧な生活を営むことができる会社の実現を目指していきます。「コンプライアンス遵守・リスクマネジメント」については、揺るがない企業基盤の構築による永続的にステークホルダーから必要とされ続ける会社の実現を目指していきます。
サステナビリティに対して、まずはできること、やるべきことを着実かつ意欲的に取り組みながらも今後の社会のイノベーションに対して柔軟に取り込み、社会に対してライフスタイルの行動変容を促していきながら、ステークホルダーの期待に対して着実に応えていくことで、恒久的に社会から必要とされる企業であり続けていきます。
・KAYAMAサステナビリティレポート2024
■川崎キングスカイフロント東急REIホテル
川崎キングスカイフロント東急REIホテルは、2018年6月に「世界初の水素ホテル」として開業しました。自社で所有する燃料電池を用いた水素発電に加え、ホテルから出る食品廃棄物を発電の原料としてリサイクルし、そこで発電された電力を購入して、館内で使用しています。
また、歯ブラシやカミソリなどのアメニティ使用量削減を目的に東急ホテルズが導入している「グリーンコイン制度」に加え、一歩踏み込んだ取り組みとして、使用済みアメニティを回収し、コースターへとアップサイクルする活動も行っています。
さらに、地元の小中学生に向けて、SDGsを学ぶ教育プログラムの一環としてホテルでの受け入れを行い、ホテルの取り組みをわかりやすく紹介することで、サステナビリティへの理解を深める機会を提供しています。
環境負荷の高いホテル産業だからこそ、私たちは「地球にやさしいホテル」「まちにやさしいホテル」「ひとにやさしいホテル」という3つのサステナビリティの目指す姿に沿って、SDGsの観点を深く認識しながら、持続可能な社会の実現に向けて取り組んで参ります。
■NPO法人環境自治体会議環境政策研究所 理事長 小澤はる奈
持続可能な社会づくりは、未来の理想論ではなく、今の地域の暮らしを守り豊かにする実践です。自治体がサステナビリティに取り組むことは、気候変動や災害リスクへの対応力強化、地域産業や雇用の新たな創出、そして住民や企業との協働によるまちの誇りづくりへとつながり、これらのことが地域の魅力を確実に高めます。
こうした効果を現実の施策へと落とし込むためには、行政の担当者が所管業務の枠を超え、地域を横断的に捉える視点を持つことが重要です。生活者の立場で社会の変化を感じ取り、それを施策に反映させる姿勢も重要であると考えます。一方、行政は担当者の異動が避けられないため、個人に依存しない仕組みとしての継続性を確保することが実務上の大きな課題と言えます。
私たちは、自治体の環境政策の計画策定や改定、進行管理を支援し、仕組みとして持続的に進められるよう伴走しています。また、環境マネジメントシステムによって、担当者が変わっても改善のサイクルが継続できる体制づくりを支援しています。加えて、脱炭素・SDGsに関する人材育成や、次世代の活動支援を通じ、地域全体に取り組みの担い手を広げています。
サステナビリティは、地域運営を持続可能にするための実務的な条件です。行政の一歩一歩の取り組みが、地域の未来を大きく変えていきます。私たちはその伴走者として、共に歩み続けます。
■株式会社クラウン・パッケージ
箱′を開ける瞬間にワクワクした期待はつきものです。商品に付加価値をつけ、保護を役目とするパッケージには、その先の笑顔を守る使命があります。
「環境に優しいパッケージにて社会に貢献する」を掲げ半世紀以上、各地域のお取引様と課題に寄り添いながらパッケージを製造してまいりました。
薄い、軽い、かさばらない極薄段ボールの「マイクロフルート」は、配送効率や省資源など環境負荷低減に有効です。搾油後のヤシカサを廃棄せずにモールドにした「ピュアパーム®モールド」や、一度役目を果たした未利用資源のアップサイクル素材「スマートパピエ®」、箱から始める社会貢献「カラフルウイッシュ®」などを組み合わせて、新しいパッケージ文化の創造を目指しています。
これから先、気候変動や人手不足など多くの課題が立ちはだかっています。
相手や未来を思いやることは、クラウン・パッケージの根本にあることとして、サステナビリティ活動を通じて従業員の自覚と自負を促していきますが、一人、一社の思いだけでは限界があります。この機会をいただいたGPN様や寄稿された企業団体様、ご覧いただいている皆様と力を合わせて、SDGsの達成を目指していきます。
・「CSRレポート」 (次号より「クラウン・レポート」に生まれ変わります!)
■コクヨ株式会社
コクヨグループは2022年、サステナブル経営指針「自律協働社会の実現に向け、ワクワクする未来のワークとライフをヨコクし、事業を通じて持続可能な社会を牽引していく。」を策定しました。
地球・社会課題を解決し、活き活きとした「働く」「学ぶ・暮らす」の実現にむけて活動し、 社会価値と経済価値の両立を目指すためです。
この指針に基づき重点課題(マテリアリティ)を設定しました。
Strategy 1 社内外のWell-beingの向上
1-1.新しい働き方の提案
1-2.ダイバーシティ&インクルージョン&イノベーション
Strategy 2 森林経営モデルの実現による事業領域拡大
2.社会価値創出に向けたマネジメントシステム変革
Strategy 3 WORK & LIFEの基盤である地球を守るための活動
3-1.気候危機への対応
3-2.循環型社会への貢献
3-3.サステナブル調達の推進
3-4.自然共生社会への貢献
2030年のチャレンジ目標及びその中間にあたる2027年目標も設定し、その目標を執行と経営とでPDCAを回していく体制を構築しています。会議体名称を「サステナブル経営会議」とし、その下部組織として、環境部会、Well-being部会、調達部会、森林経営部会を設置しています。
・サステナビリティ 2025 Webサイト PDF版
・統合報告書 2025
・統合報告書/サステナビリティサイトPDF
■コマニー株式会社
サステナビリティへの取り組みは、コマニーの経営理念の根幹とつながる重要なテーマです。私たちが目指すのは、「Empower all Life ~一人一人が光り輝く社会に貢献~」というビジョンであり、事業を通じて関わるすべての人々、そして地球環境の幸福に貢献することです 。
当社の事業は、オフィスや工場、病院などで使われるパーティションの開発、製造、販売ですが、これは単に空間を仕切るためだけではありません。私たちは、人々の関係性やそこで生まれる体験を豊かにすることを「間づくり」として価値を見出しています。この考えに基づき、震度7に耐える高耐震間仕切り「シンクロン」は、安全・安心な空間を提供することで、人々の精神的な幸福に貢献しています 。また、柔軟な働き方に対応する製品は、コミュニケーションの活性化や創造性を刺激し、働く人の空間へ貢献しています。
私たちは、理念である「人道と友愛」を大切にしながら、お客様、お取引先様、従業員などコマニーに関わるすべてのステークホルダーをパートナーと捉え、共に幸福を追求しています 。そして2030年までの目標として1億人のウェルビーイング向上やに温室効果ガス排出量を50%削減することに真摯に取り組んでいます 。これからも、関わるすべての人と企業、社会、そして地球が共に幸福になる未来を創造し続けます 。
・COMANY REPORT 2025
■株式会社コングレ
株式会社コングレは、「未来が生まれる、『場』をつくる。」を掲げ、MICE※を通じて学術やビジネス、国際交流を促進し、関連産業の振興やイノベーション、パートナーシップの創出に貢献してきました。1990年の創立以来、「よい仕事をする」「地域・社会に貢献する」「いきいきとした社員の集合体」という基本理念のもと、国際会議や学術集会の運営など、コミュニケーションの「場」を支えています。
サステナビリティは特別な活動ではなく、事業を進める基盤であり、企業が持続可能であり続けるためにも欠かせません。MICEは多くの人やモノが動くため環境負荷も大きい一方で、社会に新しい価値を生み出す力を持っています。私たちはISO20121(イベントサステナビリティ・マネジメントシステム)を運用し、環境配慮型の調達、ICTによる省資源、廃棄物削減、脱炭素化、多様性の推進に取り組み、サステナブルMICEの実現を目指しています。
MICEを「持続可能な変化を生み出すプラットフォーム」へ。コングレはその推進を通じ、学術や産業の発展、社会課題の解決に寄与し、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現に挑戦してまいります。
※MICEとは:Meeting(会議)、Incentive(研修・報奨旅行)、Convention(学会・国際会議)、Exhibition/Event(展示会・イベント)の造語です。
・コングレサステナビリティレポート
■SAGA COLLECTIVE協同組合
何世紀も続いた家業を、自分の代で終わらせるわけにはいきません。次の世代に強制するつもりはありませんが、自然と前向きに継いでもらえるような事業環境を残したいです。
気候変動はとても重要な問題で、米、海苔、ゆずなど天然素材の不作が相次ぎ、私たちのものづくりの根幹が揺らいでいます。
いま、何もしないわけにはいかないので、温室効果ガスの排出削減や、地元の自然吸収系のカーボンクレジットによるカーボンオフセットを、法人設立当初(2021年)から継続しています。3年間で368t-CO2(22.8%)を削減、886t-CO2をカーボンオフセットし、CO2の排出・吸収の地域内循環モデルを確立しました。
最近は、ネイチャーポジティブとの整合性にも注意を払っています。例えば、海洋保全に取り組む佐賀県唐津市の漁師さんや、里山保全に取り組む佐賀県基山町のNPOさんと協働しています。
佐賀の11業種12社のローカルな取り組みですが、私たちなりに考え、手を取り合いながら、行動を積み重ねています。全国各地からの視察・講演依頼、ヨーロッパの財団との交流など、活動の輪が地域を越え、世界に広がりつつあります。
やがて気候変動の緩和などグローバルなインパクトをもたらし、自然の恵みを生かしたものづくりが次の世紀も続くよう、最善を尽くしてまいります。
・サステナビリティリポート 2025
■佐賀市 総務部副理事兼契約監理課長 山口和海
SDGsの目標達成に向けて地道にサステナビリティに継続して取組んでいくことは、脱炭素社会や地域循環共生圏等の形成を通して、地域振興に寄与するという地方自治体の政策としても有益で重要かつ必要なものです。その事例となる「(佐賀の森の)木になる紙」は、市北部の山々から平野部、そして南部の有明海まで一体感のある地域振興策として、グリーン購入の出発点にあたる「買い支える社会貢献」を具体化した取組みです。
佐賀市では未利用資源の地元間伐材を活用した用紙(コピー用紙が最初で、その後は印刷用紙、封筒、ファイル等へ拡大)の全庁調達を開始し、環境保護、森林保全、林業経済支援(還元金支給)、地産地消などの政策効果を同時に目指す多面的で総合的な行政運営をしていくことで、サーキュラー・エコノミーを実践しています(現在も継続中)。
開始時の平成21年度から令和6年度までの過去16年間の調達実績がもたらした成果は累計で、間伐推進面積が約987ヘクタール、CO2の吸収量が約4,487トン、還元金の支給額が約2,560万円、国内CO2削減量が約506トン(カーボン・オフセット機能付商品購入)となり、これらはもし取組んでいなかったら得られなかった成果です。
そして、取組みの付加価値を高めるために、令和4年度からは新たに炭素取引(J-クレジット)制度の活用も始めました。これは、「木になる紙」の調達実績に基づいた炭素価値(カーボン・クレジット:累計116トン)を無償で取得して佐賀市のCO2総排出量と相殺し、市自らの排出量削減に活用しています。さらに、令和6年度からは市内全約10万世帯に毎月宅配する市政広報誌(印刷用紙)の作成経費に「森林環境譲与税」の充当を開始し、より低コストでの調達となるよう効率的に取組んでいます。
・『令和7年度 e-ガイド(環境報告書)』< P27〜P29 参照 >
■有限会社サステイナブル・デザイン
私が「サステイナブル」に出会ったのは1990年の夏でした。当時、Sustainable Development(持続可能な開発)という概念は生まれたてでした。以来35年、「サステイナブル」をライフワークとしています。
良好な環境が健全な社会の基盤となり、健全な社会が幸福な人生の基盤となります。良好な環境と健全な社会を実現し維持している状態が「サステイナブル」です(と私は考えています)。
逆を考えてみましょう。劣悪な環境・破綻した社会で、幸福な人生を実現するのは難しいですね。そんな環境・社会を次の世代(端的にいえば子供たち)に残すことに喜びを感じ、積極的に望む人はいないでしょう。「サステイナブル」に無関係・無縁な人はおらず、そういう意味で「No one will be left behind」(誰一人取り残さない)なのです。
「サステイナブル」に貢献し続ける会社は、人々から求められ感謝され愛され続けますから、つぶれません。会社の長期存続(ゴーイングコンサーン)を考えるならば、「サステイナブル」に事業・組織として取り組まない理由はありません。
2002年に創業した当社の使命は、「サステイナブルな社会・会社・人生をデザイン(設計)する」こと。そのためのコンサルティング・サービスと教育学習支援サービスを提供しています。ご興味をもたれましたら、会社HPのほか下記もご参照いただければ幸いです。
・まるっとサステイナブル、「まるサの男」
・note毎日配信「デイリーSDGsニュース」
■札幌市円山動物園 保全・教育担当係長 佐竹 輝洋
札幌市では、北海道の中心都市として、2018年に政府が開始した「SDGs未来都市」制度の初年度選定29自治体の1つに選ばれ、率先してSDGsに取り組むなど、まちのサステナビリティの向上を通じた価値の向上に率先して取り組んでいます。特に札幌市は約196万人の人口を擁する大都市ですが、そこで消費する資源やエネルギーの多くは市外から購入することで市民生活が成り立っています。
それらの資源やエネルギーを海外を含めた外部に頼ることは、社会情勢の変化に対するリスクでもあり、資金の域外流出にもつながってしまうことから、その消費を持続可能な形にしていくことは北海道内の経済循環の視点からも大変重要な取組です。
その消費を考えるきっかけの1つとして、札幌市は2019年には国内5都市目のフェアトレードタウンに認定されるなど、様々な取組を進めています。また、札幌市円山動物園においても、昨年、「オランウータンとボルネオの森」という施設をオープンさせ、オランウータンの生息域であるボルネオ島におけるパームオイルを生産するパームヤシのプランテーションによる森林破壊や動物たちの現状なども伝えているところです。
今後も、環境・経済・社会の持続可能な循環をつくっていくための取組を様々な主体とともに推進していきたいと考えています。
■サラヤ株式会社
サラヤ株式会社が活動を支援しているゼリ・ジャパンは廃棄物をゼロに近づける「ゼロ・エミッション」を目指すNPO法人(理事長 更家悠介 (サラヤ株式会社))であり、20年を渡って種々の調査や研究、イベントを実施してまいりました。
対馬市は日本における海ゴミの最前線で、多くのゴミが中国や台湾、韓国から流れてきます。この現状を踏まえ、アジアや太平洋の島国における、海ゴミ削減のイニシアチブが重要との認識を持ちました。ゼリ・ジャパンは2021年9月に対馬市と連携協定を結び、漂着海ゴミの削減と、これをベースに島国モデルを開発する予定です。
また、ゼリ・ジャパンが2019年のG20における「大阪ブルーオーシャンビジョン」の理念を継承し、2025年の大阪・関西万博でパビリオン「BlueOceanDome」の出展協力をしております。テーマはプラスチック海洋汚染の防止、海の持続的活用です。展示と並行して、様々なブルーオーシャン・プロジェクトを企画・実施し、少しでも問題解決につながるよう、「BlueOceanDome」で発表しております。9月25日に来館者様数が4月13日開催から100万人を超えました。10月13日迄、開催しておりますので、万博にお越しの際hあ、予約が必要ですがお立ち寄り頂けましたら幸いです。
■一般財団法人CSOネットワーク
SDGsを含む「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、持続可能な社会づくりに向けて「誰ひとり取り残さない」ことを誓っています。サステナビリティは環境・社会・経済の統合的取組みですが、その基盤にあるのは、人間の尊厳に根ざした「人権」の尊重です。
CSOネットワークでは、この人権尊重の取組みを公共調達を通じて広めるため、ILO駐日事務所とともに「持続可能な公共調達の推進に関する提言」を作成し、2022年12月に政府へ提出しました。その後、ILOのレポートとして刊行されています。
人権というと、長時間労働の是正やハラスメントの救済など「マイナスの是正」の側面が強調されがちです。しかし同時に、安心して生き生きと働ける職場を生み出すことは、社会に豊かさをもたらすだけでなく、企業にとっても持続可能性を高める『プラスの価値』となります。サステナビリティの意義を、こうした前向きな可能性として共有できればと願っています。
■ジット株式会社
ジット株式会社はリサイクルインクカートリッジの製造販売をメイン事業として持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。現在使用済みのインクカートリッジの年間の回収個数は2500万個を超えて毎年、回収数量が上がっています。1927トンのCO2の排出抑制を実施しておりこれは杉の木、訳15万本が吸収する量に相当します。国内で26000か所以上に回収ボックスを設置して回収の増加に取り組んでいます。また、使用済みインクカートリッジの選別作業は弊社のグループ法人のNPO法人(たいよう)が担当しています。現在100名を超えるハンディーキャップを持つ人が仕事をしています。働く場所の提供も含めて今後も弊社はサスティナブルの推進に向けて取り組みます。
■株式会社スーパーホテル
スーパーホテルはホテル業界唯一のエコ・ファースト企業として「人を元気に、地域を元気に、地球を元気に」というパーパスに基づき、お客様参加型のSDGs推進活動に力を入れております。
2024年には、2009年より継続している「ECO泊」を進化させた「CO2実質ゼロ泊」を開始、電気は再生可能エネルギーを使用、ガス・水道から発生するCO2排出量は100%カーボン・オフセットすることにより、宿泊時に発生するCO2(Scope1,2)を実質ゼロにしております。
ECO泊は公式サイトおよびPremier店舗の予約のみを対象としておりましたが、CO2実質ゼロ泊では対象を全宿泊に拡大、2009年から累計で約3000万泊を達成しております。
また、カーボン・オフセットに使用するクレジットの創出先とはクレジット購入以外にも、現地での社員の環境研修や店舗での木材活用などで連携しています。さらに、新規開業の際は出店地域の地産資源を家具の一部に使用するなど、様々な形で地域と連携しながら森林保全や地域活性化に寄与しています。
今後も宿泊産業として、スーパーホテルにお泊り頂くことでSDGsや脱炭素、地域創生などサステナビリティについて考えるきっかけとなり、お客様参加型の活動に参加いただくことで、未来につながる持続可能な社会の実現を推進してまいります。
・スーパーホテル SDGsレポート2024
■スーパーバッグ株式会社
スーパーバッグはおかげさまで創業120周年を迎えました。120年間の様々な社会の変化の中で、現在は第2次中期経営計画において“環境と共に歩む次世代パッケージ企業”をメインテーマとし、活動をしています。
サステナビリティへの取組みは、当社としても今後の150年或いは200年企業を目指すうえで重要な課題と捉えています。当社の主力製品の紙袋や紙器ではFSC認証紙などの環境対応紙の拡充や、水性フレキソ印刷の更なる深化。リサイクルプラ活用への取組みも引き続き行ってまいります。
これまでの120年間の知見を活かし、当社として何ができるのか・何をしていくべきなのかを常に模索しながら、目標の一つでもある2030年にあるべき姿として“お客さまと共に地球を大切にする、環境パッケージのフロントランナー”となるべく、歩みを進めてまいります。