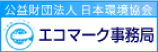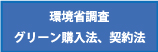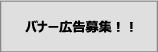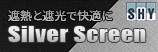- 【情報提供】CIRP LCE/Design 2026 サイドイベント GINP ワークショップ in Japan― 企業実務に活かす「絶対的サステナビリティ」 ―Absolute Environmental Sustainability(AES)を測り・設計し・実装する(3/13・神奈川,3/17・東京)
- 【情報提供】デジタルトリプレット実践研究会 公開シンポジウム「暗黙知のデータ価値化を切り拓くデジタルトリプレットーデジタルツインからデジタルトリプレットへ進化する日本型ものづくり」(4/14・東京)
- 【環境省】「環境表示ガイドライン」の改定案に対する意見募集(2/16~3/17)
- オンラインミニセミナー「サーキュラーエコノミーを加速する水平リサイクル・アップサイクルの取り組み」【埼玉GPN】(3/11)
- 事務局臨時閉局のお知らせ(2/16 11時~16時)
【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表②(2025年度)
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、「持続可能な調達(消費と生産)の推進を通じて、SDGsの目標達成やカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します」という活動方針のもと、セミナー等を通じて、サステナビリティの様々なテーマの情報発信に取り組んでいます。
今回、特別企画として、SDGsが採択された9月25日に合わせ、GPN会員団体・アドバイザーより、SDGsの目標達成に向けて、サステナビリティに取り組む重要性・必要性をテーマにメッセージを募集し、52団体(アドバイザーを含む)の方にご協力いただきましたので、ご紹介いたします。
メッセージは、2つの記事にわけております。

【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表②(2025年度)
<団体等五十音順>
・株式会社スキルアップNeXt
・株式会社セレスポ
・台東リサイクルネットワーク
・大和ハウス工業株式会社
・株式会社タカラトミー
・株式会社TBM
・TCO2株式会社
・デジタルグリッド株式会社 執行役員 松井英章
・株式会社東京ドームホテル
・中谷隼GPNアドバイザー(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 地域循環共生システム研究室)
・ニチバン株式会社
・公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
・日本生活協同組合連合会
・公益財団法人日本野鳥の会
・株式会社野毛印刷社
・Permanent Planet株式会社 代表取締役 池田 陸郎
・株式会社文伸
・ホットマン株式会社
・松本真哉GPNアドバイザー(横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授)
・武蔵野大学工学部サステナビリティ学科 教授 髙橋和枝
・株式会社モスフードサービス
・やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニック
・横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局
・株式会社 リコー
・株式会社レゾナック・ホールディングス
・株式会社ワークスタジオ
【SDGs特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN会員団体からメッセージの公表①(2025年度)
■株式会社スキルアップNeXt 代表取締役 田原 眞一
地球温暖化がもたらす気候変動は、もはや単なる環境問題ではなく、原材料調達の不安定化やサプライチェーンの寸断といった形で企業経営に直接的な影響を及ぼしています。このような状況下で、持続可能な社会の実現を目指すグリーン購入の重要性は一層高まっています。しかし、製品やサービスの環境負荷を正確に評価し、真に持続可能な選択を行うためには、GHG排出量算定に関するより深い理解が不可欠です。
当社は、この喫緊の課題に応えるべく、企業が自社のサプライチェーン全体でGHG排出量を正確に把握し、削減策を策定・実行できるよう、体系的な知識習得の機会を提供しています。具体的には、「GX検定」や関連講座を通じて、GHG排出量算定を含む、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に関する実践的な知見を学ぶ場を設けています。
GXを含むサステナビリティへの取り組みは、企業の事業活動に深く根ざしたものでなければなりません。単なる規制対応ではなく、新たな事業機会の創出や企業価値の向上に直結する戦略的テーマです。私たちは、GXの社会実装をさらに加速させるため、より多くの企業やビジネスパーソンが、実践的な知識を習得できる機会を提供し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
■株式会社セレスポ
セレスポは、「イベントを通じて笑顔のある明るい社会づくりに貢献する」ことを経営理念とするイベント制作会社です。これまでも脱炭素、資源循環、DE&Iを軸としてサステナブルなイベント制作に取り組んでまいりました。
イベントは新たな取り組みが生まれる機会であり、参加者のリアルな体験を通じて取り組みが社会に広まるコミュニケーションツールと言えます。一方、より多くの人やモノが移動し、資材を大量に使用するため、環境負荷が大きいという側面もあります。だからこそ、私たちはネガティブなインパクトを抑えながら、ポジティブなインパクトを社会に広めていけるイベントをつくり、そこにはさまざまな方に楽しんでいただきたいと考えています。そういうイベントをパートナーとの協働により一つひとつ実現していていきます。
■台東リサイクルネットワーク
社会活動が大きくなる毎に当たり前のように廃棄物が増えてくる。そんな社会は誰も望んでいないはずなのに、立ち止まって考える人が少ない。大量廃棄に使っている税金を減らし、心からの豊かさを感じることのできる社会にしたいと活動を始めました。
想いとは裏腹に社会全体は一向に望む方向に進んでいないように感じています。GPNを通じて知る事業者の取組は、持続可能な社会を形成する方向に舵を切っている事は理解できるのですが、消費者の行動がなかなかそこに追随していかない。もどかしい想いを常に持っています。
イベントで使い捨てプラスチック容器をなくしたいと、活動しています。環境イベントではある程度の理解は得られますが、お祭り的要素の強いイベントでは、面倒がられてまだまだ快く受け入れてもらえるようにはなっていません。粘り強く関わっていくことが必要だと、心しています。
3年前くらいから気候変動の危険性が一段違うフェーズに入ったかな?と感じています。それまでは局地的に起きていた事象が全世界的に顕在化してきました。既に個人レベルの努力では回避できないと言われていますが、手をこまねいていることも出来ません。一緒に行動してくれる若者たちへの責任からも、持続可能な社会を残す努力を続けて行こうと考えています。
■大和ハウス工業株式会社
大和ハウスグループは、「世の中の役に立つからやる」という創業者の想いとともに歩んできました。その精神は、当社グループの基本姿勢である「共に創る。共に生きる。」に受け継がれ、私たちの道標となっています。私たちは、この「共創共生」を基本姿勢に、事業を通じて社会に新たな価値を創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。
当社グループは、2025年に創業70周年を迎え、創業100周年となる2055年に向けては、“将来の夢”(パーパス)「生きる歓びを分かち合える世界の実現に向けて、再生と循環の社会インフラと生活文化を創造する。」を掲げています。この実現に向け、第7次中期経営計画では、カーボンニュートラル戦略や人財戦略を組み込み、経済価値と環境・社会価値は両立するものとして、事業を通じて私たちがお客さまにできることを考え、提案しています。今後も、社会課題があるところに事業機会を見出し、サステナビリティ経営を加速させていきます。
◇大和ハウスグループの“将来の夢”
◇Road to 2055 と マテリアリティ
◇サステナビリティ
◇大和ハウスグループのSDGs
■株式会社タカラトミー
私たちがサステナビリティ活動を通じて実現したいこと、
それは、サステナビリティビジョンである
「アソビへ懸ける品質は、持続可能なウェルビーイング向上にグローバルで貢献できる。」です。
「おもちゃ」における安心・安全な品質という枠にとどまらず、
「アソビ」という体験を通して、
社会性や倫理観、想像力や冒険心、
感性やひととの絆まで届けられるものこそ
わたしたちが目指すべき“品質”です。
そんなタカラトミーグループの“アソビに懸ける品質”が、
世界中のひとを健やかに、社会を賑やかにしていくことに繋がると信じています。”アソビ”には、国や文化、年齢など様々な違いを超えて子どもたちを笑顔にするチカラがあります。
私たちは、“アソビ”を通じて持続可能な社会の実現に貢献し、
そして自らも持続可能な企業へと進化してまいります。
■株式会社TBM
株式会社TBMは、「進みたい未来へ、橋を架ける」というミッションを掲げ、事業を通じて社会課題の解決に挑んでいます。
私たちは、プラスチックや紙の代替となる新素材LIMEXを開発し、世に広める過程で、「良い素材をつくるだけでは社会全体の持続可能性は実現できない」という現実に直面しました。使用後の資源循環や排出量を正しく把握する仕組みづくり、そしてそれに賛同してくださる皆様がいなければ、真の解決にはつながりません。
だからこそ私たちは、リサイクルプラットフォームの構築や、CO₂排出量可視化クラウドサービス「ScopeX」の提供へと挑戦の領域を広げてきました。技術・仕組み・価値観のイノベーションを三位一体で進めることこそが、TBMならではのサステナビリティ経営であり、世界に対して日本から提示できる独自のモデルだと考えています。
気候変動や資源制約が待ったなしの課題となる中、企業が果たすべき役割は「自社の取り組み」にとどまりません。サプライチェーンや地域社会と共に歩み、産業構造全体を変えていくことが必要です。TBMは、パートナーと連携したGX研修や自治体との資源循環プロジェクトを通じて、環境と経済を両立させる道筋を実装し続ける企業でありたいと考えています。
・Sustainability Report 2025
■TCO2株式会社
当社の企業理念は2008年の創業時より一貫して「世界地図を書き直さなくてはならなくなる前にできるコトを喚起・促進するすべての事業に積極的に取り組む」です。
人類は、歴史上最高の繁栄を成し遂げながらも、気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、格差の拡大など、地球規模の問題に直面しています。これらのサステナビリティをめぐる課題は複雑に絡み合い、単一の視点だけではその全体像を把握することは困難です。我々の文明の繁栄を支える多くの道具やインフラは、原材料の採取から製造、物流、使用、廃棄に至るまで、多様な段階で環境負荷社会負荷を発生させ、温室効果ガスの排出を筆頭に、水資源枯渇、大気汚染、生態系への影響など多岐にわたります。さらに、これらの影響は互いに因果関係を持ち、改善策が別の領域に新たな負荷のホットスポットを生み出すこともよくあります。グローバルにつながった社会で真に持続可能な社会の実現には、部分的な最適化ではなく、全体像を科学的に把握し、因果関係を明確にしながら施策を打っていくことが不可欠ですが、その可視化の有力な手法の一つがLCA(ライフサイクルアセスメント)です。
弊社は「LCAで持続可能な未来を共に」というキャッチフレーズのもと、お客様がサステナビリティを経営戦略の中心に据えるための支援を行っています。科学的事実に基づき、透明性、品質、精度に基づいた意思決定を支援し、ビジネス価値と環境価値を両立させる道筋を描くパートナーです。国内外の豊富なLCA(ライフサイクルアセスメント)データベース、環境負荷を定量的に把握するための最新のツール、数多くの実績に基づいたコンサルティング、トレーニングといったサービスを通じて社会全体のサステナビリティを推進してまいります。
■デジタルグリッド株式会社 執行役員 松井英章
再生可能エネルギーが主役になる時代を支えるためにデジタルグリッドは立ち上がりました。
発電量がそのときの天気によって変動する再生可能エネルギー電源を、 デジタル技術により今後のエネルギー供給の主役とし、 人類をエネルギー制約から解放するのが我々のチャレンジです。
世界が今日まで依存してきた石炭や石油といった化石燃料にかわり、地球の自然の力で半永久的に利用可能な新しいエネルギーを増やし、 持続可能な社会を後世に残していきたいと思っています。
デジタルグリッド(株)は、電力の発電家と需要家を直接的に結び付ける全国初の電力取引プラットフォーム(DGP)を稼働させています。電力事業では調達量と供給量を30分毎に一致させることが求められますが、当社では気象情報を基にAIを活用して需給予測を行い、需給マッチングに活用しています。近年では、遠隔の追加的な太陽光発電などの再生可能エネルギー電源を直接的に活用したいという「コーポレートPPA」のニーズが高まっていますが、DGPを活用しフィジカルPPA方式、バーチャルPPA方式ともに積極的にサポートさせて頂くことで世の中の再エネ普及への貢献を目指しています。発電家と需要家の出会いの場として、マッチングプラットフォームである「RE Bridge」も運営しています。その他、FIT非化石証書代理調達のサービスも提供しており、再エネを活用したい需要家の皆さまの様々な形のニーズにお応えするべく、サービスラインナップの充実化も図っています。また、再エネ普及により求められる調整力拡大ニーズに対応するため、蓄電池アグリゲーションサービスも積極的に推進しています。
需要家の皆さまの再エネを活用したいという声、発電家の皆さまの再エネを使って欲しいという声にお応えし世の中の再エネ普及にお役に立てればと全従業員尽力しておりますので、ご関心のある方はお声がけ頂ければ幸いです。
■株式会社東京ドームホテル
東京ドームに隣接し、都心最大級のエンターテインメントエリアである東京ドームシティ内に位置する当社は、2000年の開業当初より「楽しさ度ランキングNo.1ホテル」をビジョンとして掲げ、お客様の“楽しさ”だけではなく、働く従業員もそれぞれの“楽しさ”を日々追求しながらサービスを提供し、今年で開業25周年を迎えました。
近年、企業活動において、経済価値に加えて環境価値や社会価値がより重要視されるようになり、「持続可能な観光」の一翼を担うホテル業として、私たちは「将来世代のニーズを損なわずに現役世代のニーズを満たす商品開発」を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく必要があります。
当社では東京ドームシティの他施設と連動した省エネ関連設備の導入や、プラスチック使用量削減など、大型施設として環境負荷低減への影響力が大きい取り組みはもちろんのこと、今年度はご家族でサステナビリティについて学べる体験型イベントや、地域の学校と連携した展示企画などを実施いたしました。これらを通して、経済、環境、社会の3つの側面において、すべての人々が楽しさと豊かさを享受できる持続可能な社会を築くことに尽力してまいります。
・サステナビリティレポート2024
■中谷隼GPNアドバイザー(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 地域循環共生システム研究室)
サステナビリティとは何でしょう? 企業の皆さんは、自社のアクションが本当に「サステナビリティ」のためになっているのか、不安に思うことはないでしょうか。そう思うのも無理はありません…というより、そう思うことの方が大事だと思います。サステナビリティの中で重視される問題は、常に変化しています。例えば、今ではサステナビリティの要素として当たり前になった海洋プラスチックの問題も、筆者の印象では、10年前に急に騒がれ出した問題です。そして、現在進行中のプラスチック条約の議論では、海洋プラスチックとプラスチック汚染はイコールではなく、あくまでプラスチック汚染の一要素という位置付けになっています。そのような不確実な状況だからこそ、企業の皆さんには漠然と「サステナビリティのため」ではなく、自社のアクションが具体的に何の問題解決に貢献しているのか、深く考えていただきたいと思っています。国際的な議論にアンテナを張りつつ、その風潮に流されることなく、芯の通った多くのアクションが日本企業から発信されることを期待しています。
■ニチバン株式会社
ニチバングループは、1918年の創業以来、「貼る」を原点とする粘着技術を活かした製品を通じて、皆さまの豊かで快適な生活に貢献しています。
当社のサステナビリティは、「私たちは絆を大切にニチバングループにかかわるすべての人々の幸せを実現します」という基本理念に基づいています。創業から受け継がれてきた理念の実現を、サステナビリティの基盤としています。
気候変動をはじめとする環境・社会課題は「待ったなし」と認識しています。当社では、サステナビリティの重要課題として「気候変動・地球温暖化対策」や「環境・社会課題の解決に貢献する製品開発」、「感染予防対策への貢献」、「製品の品質向上と安全の確保」を設定しています。
再生可能な天然素材を使用し、100%グリーン電力で生産する「セロテープ®」や、使用済み粘着テープの巻心を回収・リサイクルする「ニチバン巻心ECOプロジェクト」など、具体的な取り組みを推進し、持続可能な社会の実現を目指します。
・ニチバングループ統合報告書2025
■公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)は、持続可能な社会の構築に向けて、消費者自らがライフスタイルを見直し、消費行動を変えることができるようになるためには、消費者と事業者の双方に積極的に働きかけることが大切と考え、調査研究、政策提言、教材開発、講師派遣、人材育成等、多様な活動を展開してきました。
サステナビリティが世界共通の目標となり、エシカル消費の重要性が広く認識されつつある今、企業や行政との連携を一層強め、人と自然に配慮されたモノとサービスがあたりまえになる社会をつくっていきたいと考えています。
全国組織であることを活かし、各地で講座を開催するほか、企業等の持続可能な社会形成に向けた取組みをヒアリングし、消費者や他の事業者様などに知っていただく、そんなリエゾンの役割を果たすべく、「リレーインタビュー~持続可能な社会に向けて~」を行っています。
■日本生活協同組合連合会
生協は、消費者自らがよりよいくらしを実現するための協同組合であり、「人間らしいくらしの創造と持続可能な社会の実現」を理念に掲げています。
2015年、国連の場で持続可能な開発目標(SDGs)が採択されました。私たちも2018年、「コープSDGs行動宣言」でSDGsの実現に貢献することを約束しました。
2021年には「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を策定しました。これは持続可能な社会を実現するために全国の生協で推進する2030年までの政策です。
エシカル消費の推進、温室効果ガス削減、再生可能エネルギーの開発、プラスチックと紙使用量の削減、回収・リサイクルの推進、食品廃棄物の削減、生物多様性の保全、人権尊重の取り組みなどを盛り込んだ「10の行動指針」と、将来ありたい姿をイメージしながら設定した「2030目標」によって構成されています。
私たち生協は、『すべての人々が人間らしく生きられる豊かな地球』を次世代へ手渡せるよう、組合員をはじめさまざまなステークホルダーと協働しながら本政策に取り組み、SDGsの実現に貢献します。
・生協のサステナビリティレポート
■公益財団法人日本野鳥の会
(公財)日本野鳥の会は、1934年に創設された自然保護団体で、野鳥をシンボルに生物多様性の保全と、野鳥と人が共存する社会の実現を目指しています。2030年を目標年として『絶滅危惧種の保護と野鳥の生息地保全』『地域の自然が地域の手で守られる社会』『生きものや自然に配慮したエネルギーシフトの実現』『自然への理解者の増加』『自然保護を担う次世代の育成』という5つのビジョンを設定し活動しています。
生態系の上位にいる野鳥を守ることは、多様な生き物が暮らす自然と生物多様性の保全につながります。当会ではSDGsのゴール7、14、15に関連して、シマフクロウなど絶滅危惧種の鳥を守るために、生息地購入による野鳥保護区の設置、巣箱による繁殖のサポート、政策提言活動等を行っています。また、大量生産・大量消費社会が生み出したプラスチックごみから海鳥を守るための事業や、風力発電など再生可能エネルギー施設の鳥への影響の軽減や自然に配慮したエネルギーシフトに取り組んでいます。
私たちの生活や経済、社会を成り立たせるために、森林、海洋等の生態系の保全は不可欠で、生物多様性が守られることで、私たちに自然の恵み(生態系サービス)がもたされます。生物多様性の保全は、地域の自然が地域の担い手により守られることが大切で、当会では全国85支部(連携団体)の会員と連携・協働し、その保全、回復及び持続可能な社会の実現を進めていきます。
■株式会社野毛印刷社
野毛印刷社は、印刷業の責任として、森林認証紙等の環境配慮資材の普及に努めているほか、近年は特に「子ども向けの防災教育」に力を入れ、災害に強いサステナブルなまちづくりを推進することで、SDGsの目標1・2・4・11・13等に貢献しております。
印刷会社がなぜ防災教育?と質問をされることがありますが、印刷業の役割は「必要な情報を効果的且つ分かりやすく伝えること」ですので、教育とは実は親和性がとても高いのです。まして、災害の多い日本で、防災教育を進めることはとても重要です。必然的な使命として、防災教育を通じたサステナビリティの推進に、当社は今後も取り組んでまいります。
■Permanent Planet株式会社 代表取締役 池田 陸郎
私たちは、次世代に責任を持ち、より良き世界を渡していける社会づくりを目指し、「未来に地球を残す会社」をヴィジョンに2022年に創業しました。
現在世界は、膨大な社会・環境課題に直面しており、これまで歩んできた社会・経済構造や消費行動など、あらゆる価値観を大きく変える必要に迫られています。
しかし、自分が去ったあとの未来のために、いま手にしている便益を捨てたり、変化を受け入れる勇気を持つことは難しく、社会は易きに流れ、沸騰した地球、汚染された自然という進路へ今日も世界中がアクセルを踏み続けています。
当社は、こうした世界を変えるべく、今を生きる世代としての責任を自覚し、行動を開始する企業を一つでも多く増やすため、経営層から担当者に至るまであらゆる場面へのサステナビリティ支援を続けております。
そして、国内各地の小中高生に対し、より良き世界を作る当事者としての意識と知識を持ってもらう「次世代教育プロジェクト」を創り上げ、地域で自律的に次世代同士が未来を考えていける社会づくり継続してまいります。
2030年のSDGsの更に先へ向けて、一緒に未来を作りましょう。
■株式会社文伸
株式会社文伸は、東京・三鷹の地で63年にわたり、印刷・情報発信の分野に携わってきました。
私たちが大切にしてきたのは、お客さまと地域社会をつなぎ、未来へ残す価値を形にすること。単なる印刷物の製造にとどまらず、「人に伝える・人とつながるをお手伝い」を実践しています。
サステナビリティへの取り組みは、その延長線上にあります。印刷工程で使用する用紙やインクの選定、省エネルギー型機器の導入、廃棄物削減といった環境配慮はもちろんのこと、地域学校との交流やイベント支援など、人と人をつなげる活動も持続可能な社会づくりの一端と考えています。
いま、気候変動や資源制約が深刻化するなかで、企業は事業の根幹にサステナビリティを据えることが不可欠です。文伸は「印刷と情報発信の力」で、小さな取り組みを積み重ね、次世代に誇れる未来を共に築いてまいります。
■ホットマン株式会社
弊社は東京都青梅市でタオルの製造販売を行っている会社です。企業理念に基づいて取り組んだ、日本初の国際認証を取得した日本製フェアトレードコットンタオルの製造・販売が評価され、2018年の第19回グリーン購入大賞の中小企業部門において大賞並びに経済産業大臣賞をいただきました。
2018年はSDGsが国連サミットで採択されてから既に3年が経過していたとはいえ、まだその言葉すら一般には大きく浸透していませんでした。企業として持続可能な社会を目指した活動を行うことは、企業活動の「選択肢」の一つとして捉えられていたように思います。しかし、この数年でサステナビリティへの取り組みは企業にとって欠かせないものへと大きく変化しました。消費者は、企業が環境や社会の問題にどのように向き合っているかを重視するようになっています。社会や地球環境と調和しながら価値を創出していくことこそが企業の存続と成長に繋がる時代へと変化したということです。
企業にとってサステナビリティへの取り組みは、もはや「選択肢」ではなく「前提」です。環境・社会・経済の三つの側面のバランスを意識して企業活動に取り組むことで、持続可能な未来づくりに繋げていきましょう。
■松本真哉GPNアドバイザー(横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授)
私たちは、化石燃料に代表される資源利用を基盤にした経済様式を20世紀までに確立し進めてきた。それまでは、資源の残存量を意識した思考が中心であり、地球や社会全体を俯瞰した視点はあまり共有されてこなかった。しかし今、将来の持続可能性を見据えた経済様式に転換する必要に、私たちは直面している。先進国では人口は減少しているが、地球全体ではまだ人口は増加傾向にある。それに伴い、利用される資源量も増加する一方である。いまだ主流である大量生産・大量消費型の経済様式と、地球環境の持続可能性が両立できないことは明白である。地球が持つ回復力を大きく超える自然資源の利用を示す評価結果もある。私たちの地球が持続可能になるためには、資源の利用と経済活動のバランスを考えた企業活動が必須である。また企業だけが取組めば良いわけではない。消費者たる市民が、持続可能な社会形成に資する消費や行動を選択する必要もある。そのためには、企業、市民、団体などの関与者全ての問題と意識の共有が重要である。
私は、将来の消費者たる児童生徒を対象とした責任ある消費のためのリテラシーに関する教育研究活動に取組んでいる。学習者が、容易に持続可能性を意識した商品や行動の選択ができる社会の実現に向け、関与者全ての取組みを期待する。
■武蔵野大学工学部サステナビリティ学科 教授 髙橋和枝
本学は、昨年2024年に創立100周年を迎えた都内の私立大学です。その工学部にあるサステナビリティ学科は、2023年に環境システム学科が改組されてできた新しい学科です。
今時の大学生の多くは、幼少期に東日本大震災を経験し、自然災害の危険性について、身をもって学んだ若者です。さらに近年では、甚大な被害をもたらす大雨や地震などの自然災害、原料価格の高騰等による商品の値上げ、さらに少子高齢化による地域格差の拡大など、さまざまな環境、社会問題にほぼ日常的に直面しており、その原因や対策に興味をもつのは当然と思われます。
そのような中、本研究室では、ライフサイクル思考にもとづくサステナブルなものづくりと環境配慮行動に人々を向かわせる仕掛に関する研究を中心に行い、学生らの問題意識に少しでもこたえようとしています。学生自らが課題を発見し、仮説を立て、それを検証する過程を大切にして、サステナブルな社会づくりに貢献する人材を一人でも多く輩出したいと考えております。
・SDGs活動白書2019 -2024
■株式会社モスフードサービス
モスグループは、日本生まれのハンバーガーチェーン「モスバーガー」を1972年に創業して以来、理念体系「モスの心」を指針とし、環境や健康、地域社会などに配慮した事業運営に力を注いできました。近年はサステナビリティ関連方針などを制定し、サステナビリティ委員会の運営を通じて、経営品質の向上を図っています。
また、事業活動のさまざまな取り組みをあらためて社会的要請に照らし、本業を通じて社会課題の解決に貢献するため、環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から事業におけるマテリアリティ(重要課題)を特定し、「食と健康」「店舗と地域コミュニティ」「人材育成と支援」「地球環境」をテーマに掲げ企業価値の向上を目指しています。
・「モスの森」
■やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニック
私たちがサステナビリティに取り組む理由は明確です。空気や水、住環境の悪化は、呼吸器や皮膚の病気を増やす大きな要因となるからです。大気汚染や住宅の断熱不足による結露・カビ、森林喪失や水質汚染は、喘息やアレルギーをはじめとする疾患の背景に直結します。医療の現場で患者さんを診ていると、環境改善なくして本当の健康は守れないと痛感します。だからこそ「消費と生産のあり方」を変えることが重要であり、医療機関として取り組む責務があると考えています。
当院は「アレルギー対応ハウス」を提唱し、断熱性・換気・自然素材を重視した住宅環境の改善を支援しています。また、クリニック運営でもLED照明や省エネ機器、電子カルテの導入、省資源化や環境配慮型医療用品の調達を進めています。さらに、WWFジャパンの法人会員として自然保護を継続的に支援し、地球規模の環境問題にも関わっています。これは単なる寄付ではなく、「未来の子どもたちと地域の患者さんの健康につながる投資」だと捉えています。
サステナブルな調達と環境保全は、患者の健康と地球の未来を同時に守る行動です。GPNの理念に共感し、地域医療の現場から持続可能な社会づくりに力を尽くしてまいります。
■横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局
地球温暖化の進行による気候変動や自然災害の頻発化・激甚化といった、将来の環境への危機感から脱炭素への関心がますます高まる中で、横浜市は2050年の脱炭素化に向けた将来像として、「Zero Carbon Yokohama」~2050年までの温室効果ガス実質排出ゼロを達成し、持続可能な大都市を実現する~を掲げています。
本市では、2002年に「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」を策定し、サステナビリティの観点からも全庁でグリーン購入に取り組んでいます。グリーン購入に取り組むことは、私たちの生活を取り巻く「環境面」「経済面」「社会面」に大きな影響を与え、持続可能な社会の構築につながります。市内最大級の事業者・消費者でもある横浜市役所が、業務を進めるにあたり必要となる物品、役務等の調達においてグリーン購入を行うことで、市民や事業者の皆様の需要転換を促していけるよう引き続き取り組んでいきます。
■株式会社 リコー
リコーグループは、「人を愛し、国を愛し、勤めを愛す」という創業の精神(三愛精神)を基盤に、「“はたらく”に歓びを」を使命とし、働く人々に寄り添い変革を起こし続けることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な未来の社会の実現を目指しています。目指すべき持続可能な社会の姿を、経済(Prosperity)、社会(People)、地球環境(Planet)の3つのPのバランスが取れた「Three Ps Balance」として表し、その実現に向け、事業を通じた社会課題の解決や経営基盤の強化、社会貢献活動に取り組んでいます。サステナビリティは事業成長や企業価値向上に不可欠な取り組みと位置付け、中期経営戦略の中で「ESGと事業成長の同軸化」を経営方針の一つに掲げ、お客様の生産性向上や脱炭素・循環型社会の実現に貢献する製品・サービスの提供に注力しています。
■株式会社レゾナック・ホールディングス
レゾナックは2023年に昭和電工と日立化成が統合して誕生した機能性化学メーカーです。パーパス「化学の力で社会を変える」に基づき、先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出することでグローバル社会の持続可能な発展に貢献し、「人々の幸せと豊かさ」「地球との共生」を実現することを目指しています。
その一環として、「サステナビリティビジョン2030」を設定するとともに、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)を特定し、非財務KPIを定めて取り組むことで長期ビジョンの達成につなげています。また、バリューチェーンの川上から川下まで幅広い領域で提供している当社の製品・サービスが、顧客や社会にどのような価値を、どのくらい提供することができたかを可視化する「Resonac Pride 製品・サービス」などにも取り組んでいます。
共創型化学会社として「個の力の向上」と「企業文化の進化/深化」に取り組むレゾナック。価値創造を進める私たちの思いや取り組みについて、詳しくは統合報告書「RESONAC REPORT 2025」をご覧ください。
・サステナビリティ | レゾナック (resonac.com)
・環境 | サステナビリティ | レゾナック (resonac.com)
■株式会社ワークスタジオ
「廃棄は終わりではなく、未来の始まり。」
これがPANECOの変わらぬ想いです。
なぜ私たちはサステナビリティに取り組むのか――それは、次の世代により豊かな未来を手渡すためです。大量に生産し、大量に廃棄するこれまでの社会の仕組みを続ければ、地球の資源も環境も限界を迎えてしまいます。だからこそ、廃棄を「終わり」ではなく「新しい始まり」と捉え直すことが、今の時代に求められているのです。
PANECOは、まず「衣」にあたる社会で不要になった繊維廃棄物を再資源化し、再生ボードとして循環させる技術を確立しました。それは、単に廃棄物を減らす取り組みではなく、資源を大切にしながら新たな価値を生み出す挑戦でもあります。
さらに「食」の分野でも、食品廃棄物を資源へと変える循環の仕組みを築こうとしています。日々の暮らしを支える衣・食・住をすべて循環型へと転換することこそ、持続可能な社会を実現するために欠かせない道だと信じています。
「廃棄を価値へ。未来を切り拓く。」
PANECOは、人と地球が共に笑顔で生きていける未来を目指し、挑戦を続けてまいります。